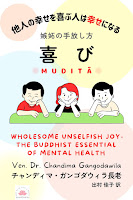なぜ、言葉が大切なのか?
「なぜ、言葉が大切なのか?」と聞かれることがあります。
私たちは普段、何気なく話しています。まるで空気のように言葉を使っています。なかには「自分は思っていることをそのまま口に出して言う。それが自然体だ」と言う人もいるでしょう。
一見、ないがしろにされがちな「言葉」ですが、ブッダは最も重要な真理である「八正道(苦しみを滅する8つの道)」のひとつに「正しい言葉(正語:しょうご)」を含めました。
なぜ、言葉がそれほど大切なのでしょうか?
それは、私たちの生き方に言葉が深く関わっているからです。
人はこころだけでなく、言葉を通じてものごとを学んだり、自分の考えを他人に伝えたり、相手の考えを理解したり、互いにコミュニケーションをとることができます。言葉によるコミュニケーションが、人との関係の中で重要なものとなっているのです。
たとえば、仕事では連絡や報告、アイデアなどを共有し、協働するために欠かせないツール(道具)となっていますし、学校や研修では知識を身につけ技術を習得するために言葉が使われますね。情報をやりとりするときにも言葉が使われます。
では、言葉は単に情報をやりとりするだけのツールでしかないのでしょうか?
そうではありません。言葉は単なるツールではなく、「正しく育てるべきもの」なのです。
「言葉」のことをパーリ語で vācā(ワーチャー)と言います。
この vācā を正しく使うことを「正語:sammā vācā(サンマー・ワ―チャー)」と言い、この正語を育てることによって私たちの性格も「善」のほうへと向上していくのです。
そのため、苦しみをなくしたい、「善」の道を歩みたい方にとっては、言葉の善い面である「正語」を実践することが非常に大切になります。
また、言葉を正しく使う人は他人からも尊敬されるでしょう。
「はじめに 言葉の大切さ」より
『正語〈正しい言葉:Sammā Vācā〉~幸・不幸をつくる言葉の法則 ― 八正道➂』
チャンディマ・ガンゴダウィラ長老【著】











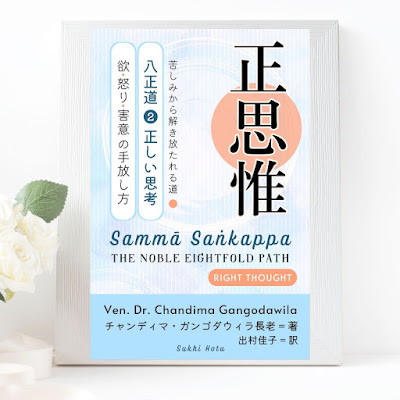






.png)