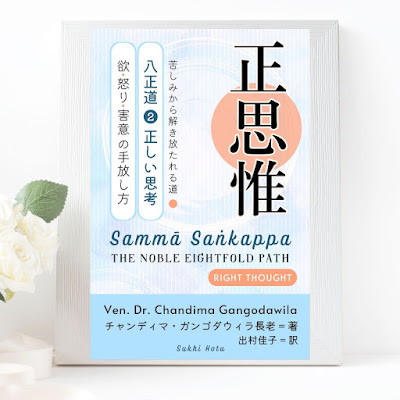『第5章 やすらぎをもたらす「正語」とは?』より
沈 黙
言葉の側面のひとつ「沈黙」についてお話いたしましょう。
私たちはときどき沈黙の中で過ごすことが大切です。口数が多いことはよいことではありません。なぜでしょうか?
・選択できる
まず、いつも誰かと話していると、こころが落ち着かないからです。
つい余計なことを口走ったり、相手の気持ちを傷つけたり、誰かの悪口を言ったり、うわさ話をしたりする恐れがあるのです。
また、自分をよく見せたい、自慢したい、認められたいがために、話を誇張したり、嘘をついたりする可能性もあります。これは善い行為ではありませんね。
ですから、話さなくてはならない用がないかぎり、沈黙を守ったほうがよいでしょう。
沈黙することで、こうした悪行為を避け、自分や他人を傷つけるのを防ぐことができるのです。
また、外部の情報に振りまわされることなく、自分のこころに耳を傾けることができるでしょう。
話すときは、無駄な言葉を減らし、本当に伝えたいことだけを的確に表現できるようになります。感情的な言動を避けられますから、よりよい人間関係を築くことができるでしょう。
「やすらぎをもたらす正語とは?」
『正語〈正しい言葉:Sammā Vācā〉
~幸・不幸をつくる言葉の法則 ― 八正道➂』より
チャンディマ・ガンゴダウィラ長老【著】