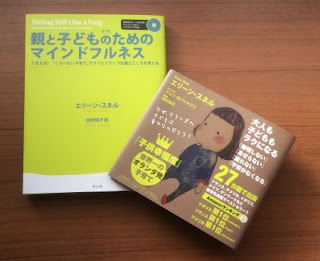2018/12/19
2018/12/09
善悪とは?③-2
功徳を積む人は寿命がある限り、善行為をたくさんします。
その人は寿命をまっとうすることができます。
他方、悪行為をする人は、寿命が終わるまで生きていられません。
不善行為をする人も、寿命が終わるまで生きることはできません。
与えられた業の寿命よりも、自分の寿命が先に終わってしまうのです。
功徳や善をおこなう人は、自分に与えられた寿命は完璧に完了します。
たとえば、生まれたときに業(ごう)によって寿命が100年となっていたら、ちょうど100年ピッタリで亡くなるのです。
功徳のよいところは、それなんです。
寿命をまっとうすることができるのです。

「寿命をまっとうする」とは、突然、難病になったり、事故に遭ったり、寿命が縮んだりすることはないということです。
功徳を積む人は、功徳行為を完成することはできませんが、寿命が終わるまで功徳を積むことができ、寿命をまっとうすることができます。
寿命が終わったら、当然、幸福なところに生まれ変わることができるのです。
「善行為(kusala)」は完成できる
一方、善行為は完成できます。
完成とは、智慧が現れて、解脱に達するということです。
善行為とは、人格を向上すること、理性を育てて正しい判断能力や観察能力を身につけること、正しい行為をすることです。それで、智慧が現れるのです。
ですから功徳行為ではなく、善行為をおこなうと、智慧が現れます。
功徳だけだと、功徳だけで終わります。智慧は現れないんです。仏典には、徳をたくさん積んでいても智慧は現れないと、はっきり言っています。
ときどき、善いことをするわするわ、誰もかなわないくらい善いことをする人がいるんです。
しかし、智慧は現れません。
いま思いだしたのはマザー・テレサさんです。彼女がおこなった行為は誰もかないません。しかし、あれは功徳行為です。智慧は現れにくいのです。
でも、彼女は普通の人にかなわないくらいの功徳を積みましたから、智慧が現れる可能性もあったようです。彼女の本を読んでみると、智慧が現れかけていた兆候が見えるのです。
インドの貧困の人をすべて完璧に面倒見ることは、いくらなんでもやりきれないことでしょう。やればやるほど、人間が不幸であることを発見していくのです。
それで、彼女は最後のほうになってくると、少し客観的に現実を観察するようになり、「なんだこれは、神が創った世界なのに不幸ばかり。やりきれない。これでは人生に納得できない」というふうに、生きることが苦であることを理解していくのです。神に縋ることは、彼女にとって答えではなかったようです。
そこで、もし彼女が、「生命は誰だって苦しんで生まれ、苦しんで生きて、苦しんで死ぬんだ」ということを理解したなら、智慧が現われ、心が落ち着いたでしょう。
彼女がどこまで理解できていたのかはわかりませんが、彼女が立派な方であったことは明らかなことです。
「善」というのは、ものごとを理解して、判断能力を正すことです。
何かを理解したということは、智慧が現れたということです。
それで智慧が完成したら、生きる問題はすべて終了するのです。
善が完成すると、功徳も完成する
善が完成すると、ついでに功徳も完成します。
功徳が自動的に完成するんです。
なぜなら、功徳は善の中にあるのだから。
生きとし生けるものが幸せでありますように
善悪とは?
①-1)まず善悪の勉強から始める
①-2)不善と悪の違い
②-1)悪と不善・功徳と善の関係
②-2)悪と不善に完成はあるか?
③-1)功徳と善に完成はあるか?
③-2)善行為は完成できる
④-1)功徳から善への進み方①
④-2)功徳から善への進み方②
⑤-1)自己を観察し「平等」を理解する
⑥-1)他の役に立つように生きる
⑦-1)「自分は悪いことをしない」と決める
⑦-2)対話と理解
⑧-1)仏道は、両目を見えるようにする
①-1)まず善悪の勉強から始める
①-2)不善と悪の違い
②-1)悪と不善・功徳と善の関係
②-2)悪と不善に完成はあるか?
③-1)功徳と善に完成はあるか?
③-2)善行為は完成できる
④-1)功徳から善への進み方①
④-2)功徳から善への進み方②
⑤-1)自己を観察し「平等」を理解する
⑥-1)他の役に立つように生きる
⑦-1)「自分は悪いことをしない」と決める
⑦-2)対話と理解
⑧-1)仏道は、両目を見えるようにする
2018/12/04
希望と欲望⑤-1
今おこなっている善行為を、完成するまで拡大する
私たちは日常生活の中でいろいろな善いことをしています。
たとえば仕事をまじめにするとか、社会が発展するよう努力するとか、そういう自分が誠意をもってやっていることがいろいろあると思います。
その「善いことをさらに完成するところまで努力する」のが3番目の希望――いわゆる「正精進(sammā vāyāma)の3番目」です。
これぐらいでいいのではないかと、ほっとしないようにしてください。私は毎朝9時から夕方5時まで仕事をしているから、それでいいのではないかと安心するのではなく、さらに「善いこと、役に立つことはないでしょうか」と、自分が日々やっている善い行為を、完成させるまで努力しなければならないのです。
たとえば、学校の先生の場合、「自分は10年間も教えてきたからそこそこ経験もあるし、教える内容も身についているし、教え方も、子供をまとめる方法も知っているから、それぐらいでよいのではないか」と安心してはなりません。
より立派なことをしようと智慧をしぼって、さらに努力することが大切なのです。
正精進④
今までしたことのない善行為をする
正精進の4番目は「今までしたことのない善行為を勇気をだしてする」ことです。
先ほどの学校の先生を例だと、今まで教科書どおりに教室で教えてきましたが、ちょっと方向を変えて、子供たちと外に出て自然のなかで授業をするとか、あるいはキャンプに行くとか。
そうすると机上の勉強では学ぶことのできない新しい発見が生まれてくるかもしれないのです。
でも、私たちはたいてい何か新しいことをしようとするとき、「やったことがないからやめよう」という弱気な気持ちが出てくるものです。善い考えは浮かぶけれども、やったことがないからやめましょうと、そういう弱さがあるのです。
これは仏教ではあまり認めていません。
仏教は、たとえやったことがなくても、それが善い行為なら、勇気をもってやりなさいと教えています。いつでも前進です。
これが4つ目の正精進であり、善い希望なのです。